飛鳥の都は亡命した朝鮮系渡来人が築いた~天皇家のルーツ
飛鳥の都は亡命した朝鮮系渡来人が築いた~天皇家のルーツ
飛鳥に係る仕事があって、飛鳥についていろいろ調べると、必ず行き着くのは鮮系渡来人である。
宮内庁が「天皇陵」の学術的調査を認めない理由は何であろうか。その答えを具体的に言えば、「天皇家の祖先」が「朝鮮半島から渡って来た証拠が出て来る恐れ」があるからだという。日本の歴代天皇の中で最も活躍した天皇の一人「桓武天皇」の母 高野新笠(たかのにいがさ)は、百済の名王 「武寧王の後裔」であることは日本史の常識になっている。ちなみに、「桓武天皇」は朝鮮系天皇「天智天皇」のひ孫である。
歴代天皇の中で最も活躍したとされる天皇「天智天皇」「天武天皇」の母「斉明天皇」は、「朝鮮人豪族 吉備王朝」の出である。吉備王朝は、朝鮮式山城を根城に、大和王朝以前 倭国最大の勢力をもっていたという。吉備には、大和王朝以前としては、日本最大の古墳があるという。従って、「天智・天武は朝鮮系の天皇」であるということになる。「白村江の戦い」で、百済救援のために、斉明天皇の後を追って、天智が3万人に近い兵を送ったということは、「百済と倭国は姻戚関係にあったからだ」と金達寿 佐々克明 洪思俊<扶余博物館館長>らは述べている。
天皇家のルーツを煙に巻いたのが藤原不比等が編纂した日本書紀であり、現在の宮内庁が認めない理由もその真実を認めているからに違いない。
日本語と韓国語は同系語http://japanese130.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-3de5.htmlより
西暦663年、「白村江の戦い」で新羅にやぶれた百済から五万人が渡来したという。このことに関して、司馬遼太郎は「百済 国ごとの引っ越し」と語っている。「日本書紀」によれば、天智天皇は、当時の亡命者を、近江の蒲生郡あたりに3000人近く住ませ、無償で農地を与え、官食を三年間も与えたという。百済の高官66名が政務次官なみに登用され、「法務大臣(法官大輔)」「文部科学大臣(学頭職)」になった人もいる。西暦667年、「天智天皇は都を近江」に移している。「額田王の父 鏡王は 近江の蒲生郡に住んでいた」と言われている。
額田王が天智の妃なったことと、くしくも、額田王が朝鮮人であったことは、天智による近江遷都には朝鮮の匂いをただよわせるものがある。額田の義母 斉明天皇が朝鮮人であり、斉明天皇の子供(天智)が朝鮮系の天皇であり、その妻が朝鮮人であることは、「近江」と「朝鮮」の関係の深さを彷彿とさせる。百済人が倭国へ亡命したのは、亡命以前から、倭国と百済には縁戚関係が成り立っていたからである。日本国の誕生にもっとも力を発揮したのは、「白村江の戦いの敗北で渡来した百済人」で、彼らによって「日本という国号」がつくられた。
「大化の改新」は、藤原鎌足(百済の渡来人)を筆頭に、安倍内麻呂 金春秋 高向玄理などの渡来人によって行われた。また、「藤原不比等」は鎌足の子で「大宝律令制定」の中心メンバーであった。不比等は「本妻の娘を文武天皇」「後妻の娘を聖武天皇」の妃とさせ、藤原氏の基盤を築いた大人物とされている。アジア古代歴史学会の会長 上田正昭らの対談集によれば、「日本書紀」は「百済人を主軸に書かれ、天皇・朝廷のプロモーター藤原氏の都合がいいように整理されている」という。
「天皇家と藤原氏は、血縁的に見れば、また遺伝子的に見れば、区別がない」という。天皇と藤原氏の娘の子である天皇が、藤原氏の娘の子を次の天皇にしていくということを繰り返したので、天皇家固有の「血」などはなくなったのである。つまり、「天皇家と藤原家は一体」である。藤原氏は強大な政治力をもち、実質天皇とも言える実権をもっていた。梅原猛は「奈良の都の政治は不比等の独壇場であった。不比等の下に集められたのは、智謀豊かな、法律、歴史に詳しい朝鮮人であった。」と述べている。
「高句麗」や「百済」にも天孫降臨の神話がある。これは「天皇家朝鮮起源説」を裏づけるものであるという。天皇の礼服の紋章には円形の中に「八咫烏」の刺繍が施されているという。「八咫烏」は「高句麗」のシンボルである。従って、「天皇の始祖は高句麗」にあるという説がある。「八咫烏」は日本古来の文化ではなく、直接的には朝鮮から渡来した文化である。
ソウル市内の国立中央博物館で韓国の「檀君神話」 と「日本の建国神話」 を比較考察する学術会議が開催された。アジア史学会会長 上田正昭氏の論文が事前公開され、「天孫が空から降りる韓国と日本の神話には類似性が多い」との記述に注目が集まったという。日韓の神話を比較研究してきた上田氏は、日韓の天孫はいずれも山頂に降臨しており、共通点が多いと主張。百済の神の存在が、日本で継続的に命脈を受け継いできたと指摘している。日本の建国神話は、韓国の「檀君神話」の影響を大きく受けており、この事実は韓国だけでなく日本史学界でも認められているという。
京都産業大学文化学部国際学科の井上満郎教授は、韓国の檀君神話と伽耶の首露王は、日本神話に登場する天孫ニニギと同じような要素を持っている。「日本の天孫降臨神話が朝鮮半島系ということは疑う余地がない」と述べている。また、韓日天孫文化研究所所長のホン・ユンギ氏は、「日本の建国神話は、天孫が降臨する檀君神話を織り交ぜて作られたもの」であり、「三種の神器」も「三種の宝器」として「檀君神話」に登場すると述べている。日本の代表的な民族学者 東京都立大学の岡正雄教授も、1949年に、これを認める発表をしているという。
学者ならぬ凡人にでもわかることは、日本にも朝鮮にも、「仏教」以前からあった「神道」の存在である。「神道」は、朝鮮半島の古代文化を形成した北方民族 (騎馬民族) のシャーマニズムに由来すると言われている。北方民族のシャーマニズムは「天孫降臨神話」をもっており、「天孫降臨神話」が日本にも朝鮮にもあるということは、騎馬民族によって形成された朝鮮文化の流れが日本にもあるということになる。弥生時代から急増した朝鮮渡来人が、倭国へ「神道をもちこんだ」のはごく自然な流れでしょう。「天皇家が古代から現在に至るまで神道を一貫して信奉していることは、天皇家が朝鮮由来の姿を留めている現れ」である。
「天皇家のルーツが朝鮮半島」にあることを示すものの一つとして、志賀島の金印「漢倭奴国王」の時代から、志賀島周辺が朝鮮半島南部の国の支配下にあったのではないかというのがある。6~7世紀に新羅によって滅ぼされた百済から大量の渡来人が倭国に亡命してきたが、彼らが倭国への侵略者に転じなかったのも、すでに確立していた同胞国家である大和朝廷に迎え入れられたからであると言われている。百済からの渡来人にとって、倭国が本拠地になり、渡来人は新しい国づくりに邁進し始めたのである。
「蘇我氏(朝鮮渡来人)」は、六世紀後半には今の奈良県高市郡明日香近辺を勢力下においていた。飛鳥が政治の中心地であったことは、「蘇我氏が政治の実権を掌握」した時代以後、飛鳥に「集中的に天皇の宮がおかれるようになった」ことからもうかがわれる。朝鮮の渡来氏族がいかに大きな力で日本国を牛耳っていたかがわかる。「蘇我氏は皇室との姻戚関係を深めて政治的権力を強化」した。物部氏を滅ぼして国政の主導権を握った。「用明、推古などの蘇我系の天皇」を擁立した。渡来人によって「日本」という国号が作られ、「天智・天武・藤原氏などによる国家体制」がととのえられ、「大化の改新」「大宝律令」などによる新しい国造りが始められた。
実質天皇であった「蘇我氏」「藤原氏」が渡来人であったことは、彼らとの姻戚関係からしても、日本の天皇は朝鮮系の人であったことは明らかである。弥生時代以後、倭国の住民の90%以上が朝鮮渡来人であったことからしても、天皇の出自がどこにあるか自ずと知れるのである。大和朝廷の構成員は、トップスター「蘇我氏」「藤原氏」「秦氏」らがすべて渡来系氏族であるからして、職員は一人残らず渡来人であるとするのが自然であろう。その構成員の長たる天皇がいかなる存在にあったかは押して知るべしである。
始原の言語・日本語の可能性~②実体と発音が一致している美しい日本語
始原の言語・日本語の可能性~②実体と発音が一致している美しい日本語
日本語シリーズ第3弾です。前回の記事で朝(Asa)というキーワードから発音体感と情景、言語が密接に連関している事を感じていただきました。今回はそれを受けてさらに日本語全体の構成にまで拡げてみていきたいと思います。
著者は日本語を美しい言語だと言う。
「サクラサク。」この5文字だけで多くの人はなんとも言えない歓喜と美しい情景を脳に描く事でしょう。チェリーブラッサムでも英語圏の人は同様に感じるはずだと思うかもしれませんが、桜の花びらの散りゆく儚さや、地面が桜色に染まっていく情景、満天の青空を背景に淡いピンク色に拡がる満開の景色、さらにそれを見上げている人々のなんとも言えない表情。それらは英語圏のこの単語では思い浮かべる事はできないでしょう。きっとサクラという樹木を思い浮かべるに過ぎません。
サクラという文字、サクという動詞の重なりが相乗して一気に情景の美しさを際立たせています。咲くという動詞は桜という名刺から誕生した事が容易に伺えます。さらに言えばサとクとラ、それぞれに桜の情景を浮かべる要素が組み込まれているからに違いありません。サクラだけでも十分に美しいのです。
日本語の美しさの理由は、このように言語と情景が一致している事にあります。
今回も同様に黒川伊保子氏の著書「日本語はなぜ美しいのか」から紹介していきたいと思います。
ことばは音韻(ことばと音の最小単位)の並びであり、その発音体感が潜在脳にしっかりとことばの象を作り上げる。
私自身は「感じる言葉の第一法則」として「ことばの発音体感と、その実体のイメージが合致していると気持ちいい」という法則をあげて来た。
情景と語感が一致している例なら、擬音語、擬態語が最もわかりやすいだろう。そもそも擬音語・擬態語は情景、状態などを語感で表現した語なのだから。
擬音語、擬態語はふつうの辞書では網羅されていない。タラタラとダラダラを辞書で引いても「タラタラする」といえば起きて動いているけど「ダラダラする」といえば座るか、寝そべっているなど、そんなことまでは書かれていない。「額から血がタラタラ出ている」のなら致命傷ではないけど「額から血がダラダラと出ている」では死を暗示しているのかもしれない。このように擬態語、擬音語の中で日本人が暗黙のうちに了解している部分は(辞書に書くまでもなく)あまりにも多いのだろう。逆に外国人が日本語を習得する際に(辞書にすらないそれらの言語は)特に戸惑う日常語でもある。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
さて、この擬態語をベースに発音と実体が日本語はいかに一致しているかを確認してもらいたいと思います。なるほどの連続になるはずなので期待して読み進んでください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
カラカラ クルクル コロコロ
サラサラ スルスル ソロソロ
タラタラ ツルツル トロトロ
縦並び(カラカラ クルクル コロコロ)はよく使われるカ行音始まりの擬音語・擬態語である。順にサ行音、タ行音という並びになっている。横並び(カラカラ サラサラ タラタラ)は音構造がほとんど同じまま、骨格をなす子音がK,S,Tに変化している組み合わせだ。まずはこの横の変化をじっくりと味わってほしい。
カラカラ、サラサラ、タラタラ。
カラカラは硬く乾いた感じ。サラサラは木綿の表面を撫でた時のような、空気を孕んですべる感じになる。タラタラになると、濡れて、粘性を感じさせる。
クルクル、スルスル、ツルツル。
クルクルは、硬く丸いものが回転する感じ。スルスルは、紐が手のひらをすべっていく感じ。ツルツルはまるでうどんをすする音のようで、汁を含んだ粘性のある物体を感じさせる。
コロコロ、ソロソロ、トロトロ。
コロコロは、硬く丸いものが転がる感じ。ソロソロは廊下をすり足で行く感じ。トロトロは粘性を感じさせる。これらK,S,Tの擬音語・擬態語展開には、同じ法則を見出す事ができる。すなわちKには硬い固体感が、Sには空気を孕んですべる感じが、Tには粘性のある液体のイメージがあるのである。
Kは固体、Sは空気、Tは液体。もちろんこれらの法則は発音体感によって生じたものである。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
さて、このK、S、Tの分析を紹介しておきたい。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【Kの硬さ】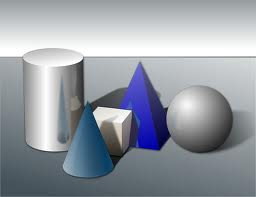
「固体のK」
Kは喉の奥をいったん閉じて、その接着点に強い息をぶつけ、ブレイクスルーして出す音である。喉の奥というのは、正確には軟口蓋と、舌の付け根、軟口蓋というのは口蓋垂(俗にのどチンコ)のくっついている場所で、ご存知のようにぐっとせり上がった形になっているため、本来、舌とはくっつきにくい場所である。
そこをあえて接着するので喉周辺と舌の付け根周辺の筋肉が緊張して、かなり硬くなる。ここに強い息をぶつけ、喉の接着点を破って出す、いわば「喉の破裂音」がKの音なのだ。これに縦に高く開いた口腔を合わせればカ、口腔を小さくして前向きの強い力で押し出せばキ、舌にくぼみを作って受身の姿勢にするとク、舌を下奥に引き込めばケ、口腔に大きな空洞をつくればコとなる。
すなわち硬く、強く、速く、ドライ、さらに丸さ(曲線、回転)を感じさせる。これこそがKが人類に感じさせている発音体感である。
カラカラ、カンカン、カチカチ、キラキラ、キリキリ、コロコロ、キリリ・・・カ行の擬音語、擬態語を並べていくと、硬く、強く、あくまでドライなイメージが並ぶ。回転の象も見え隠れする。Kの発音体感としっかり結びついているのがおわかりになるだろう。
さらに擬音語、擬態語になくても硬い、きつい、切る、錐、堅実、剣、険、頑なのように意味と語感が結びついているものも多い。
【Sの風】
「風のS」
Sは息を舌の上にすべらせ、前歯の付け根の歯茎にぶつけ、前歯でこするように出す音で、歯擦音とも呼ばれる。口の中に吹く風である為、発音体感は爽やかで涼やかだ。舌の上をすべるので、つばと混じって、ほどよい湿度感を覚えさせ、シットリしている。シットリも湿度もS音の音なのは、もちろん偶然じゃない。風を感じさせるスピード感もある。空気がすべる発音体感なので、サラサラ、シットリ、スベスベ、スルスル、ソロソロなど、サ行の発音体感は爽やかですべる感じ、適度な湿度感を含むものばかりとなる。
切なさ、寂しさ、嫉妬、しめやかなどという単語にも、何かとどまらない、すべり落ちていく不安定さと湿った感じになる。
一方、爽やか、颯爽、爽快、すっきり、スピード、スポーツなど風の象を感じさせるS音の単語群は、キャッチコピーや商品名にも多用される。スピード、スムーズ、ソフト、スポーツなどS音の語感を上手に活かした英単語は和製英語として日本人に定着しカタカナ言葉となっていった。
【Tの確かさ】
「テクノロジーのT」
このように、硬く乾いた「カラカラ、クルクル、コロコロ」のK音をS音に換えれば、すべるような「サラサラ、スルスル、ソロソロ」に変わる。湿度感が増したのも、感じていただけるだろうか。さてこのS音をT音に変えると「タラタラ、ツルツル、トロトロ」・・・・こんなにも濡れて、粘ってしまう。
T音は、上あごに舌をつけ、その接着点を息で破って出す音である。接着点がブレイクする直前、舌は息を孕んで膨らみ、弾けるように前に押し出される。舌打ちによく似た発音体験である。この音は舌の上のつばをはがすようにして口元に運ぶので、最も濡れた感じがする。舌が膨らんで、弾け、たゆたうので、粘性を感じる。また、舌が膨らむために、充実感や確かな手ごたえがする音でもある。
濡れて粘るT、タラタラ、ツルツル、トロトロの濡れて粘る理由は、発音体感に他ならない。たっぷり、たんまり、たらふく、たらり、確かさ、富むなど充実感を表現する語もTならではの味だ。
【ことばの美しさ】
私たちはこうして、事象に似た発音体感を味わいながら、ことばをしゃべっているのである。大きなものには大きな発音体感を、硬いものには硬い発音体感を、スピード感のあるものにはスピード感のある発音体感を、優しいものには優しい発音体感を・・・・そうして名を呼ぶ者は、名のもち主と響き合うのだ。
それは、音楽に合わせて踊るのと同じような、共鳴の快感を作り出す。名を呼ぶ、というのは、なんとも親密な行為なのである。(中略)私たちは、事象に似た発音体感を味わいながら、ことばをしゃべっているというより、事象に似た発音体感を味わうために、言い換えれば、魂の共鳴を感じたいがために、ことばをしゃべっているのかもしれない。
私たちは対話によって、意味を超えた、より深いものを交換しているのだ。それができる言語と、できない言語があり、それができる言語こそが最も美しいのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カラカラ、サラサラ、タラタラ・・・黒川氏の分析に、「なるほど!」と膝を打った方は多いと思います。
そして、K,S,Tだけでなく他の子音も知りたくなります。
ナ行、ハ行、マ行、ヤ行、ワ行、それらの子音群にもきっと同じような情景があるに違いありません。そしてそれらの音感体系を知り、日本語を再認識すれば、著者が言うように対話を通じて意味を超えたより深いものを共感できるような気がします。
まだシリーズは始まったばかりですが、いきなり核心に近づいてきたかも。次回お楽しみに。
始原の言語・日本語の可能性~(3)2重母音が作り出すやわらぎの意識
始原の言語・日本語の可能性~(3)2重母音が作り出すやわらぎの意識
日本語は母音言語が特徴的ですが、母音といえばアイウエオ、さらにそれを特化した2重母音といいう子音があります。
ヤ行とワ行です。
この2重母音の行は他の子音群にはない特徴を示しています。単純なひとつの感情だけでなく重層した微妙なニュアンスの表現を求める日本人を現す特徴的な言語のひとつかもしれません。今回はその2重母音の子音であるYとWを紹介したいと思います。
同じく黒川伊保子氏の著書「日本語はなぜ美しいのか」から紹介していきます。
【Yの揺らぎ】
「クヨクヨはK音じゃないの?強いドライなはずのK音が、なぜ優柔不断の擬態語に使われているんだろう?」と疑問を感じた方はいるだろうか。その気づきは、相当いいセンスです。
クヨクヨの2拍目と4拍目に使われているY音は、母音イから他の母音への変化で発音する、2重母音ともいうべき特殊な子音である。母音イからアヘへの変化「ィア」で発音しているのがヤYa、母音イからウヘへの変化「ィウ」で発音するのがユYu、母音イからオヘの変化「ィオ」で発音するのがヨYoである。
緊張のイから緊張緩和への変化が身上の発音体感なので、やわらぎの意識を作り出す。優しさとやわらかさ、弛緩とうやむやの音なのだ。他の音素と組み合わせて使えば、揺らぎを作り出す。このY音を偶数拍に使った擬態語には、ヒヤヒヤ、スヤスヤ、ソヨソヨ、クヨクヨなどがあるが、これらはすべて、揺らぎの様相を表している。
ヒヤヒヤの揺らぎは、熱量の揺らぎだ。ヒリヒリはひたすら熱いが、ヒヤヒヤは熱かったり冷たかったりする。あるいは気持の揺らぎ(「危なっかしくてヒヤヒヤする」)にも使われるが、この場合も、緊張と緊張緩和の揺らぎを表す。
(中略)
さて、問題のクヨクヨだが、ものごとをしっかり受け止めるクの意識をヨが揺るがせている。「決心したかと思ったら、また迷う」という頼りなさを表しているのが、クヨクヨなのである。強くドライなK音が、優柔不断を表す擬態語に使われている理由は、このように、偶数拍のY音の揺らぎ効果との組み合わせにある。
安らかな寝息の擬態語である「すやすや」は吐く息の音スと、それをやわらげるヤによって吸う息を示唆し、安定した呼吸を表現している。「ソヨソヨ」は風が吹いたりやわらいだりする、心地よい微風の様子であり、このように偶数拍のY音は、例外なく、奇数拍のイメージに揺らぎを与えている。
クヨクヨ、スヤスヤ、ソヨソヨ・・・なるほどですね。
他にもウヨウヨ、ナヨナヨ、ヨチヨチ、ヨロヨロ、ヨタヨタ、ヤレヤレ、ユルユルなどどれも実に揺らいでいますね。次にもう一つの2重母音Wを見ていきましょう。
【Wの攪乱】
Wはウから別の母音への変化で出す音である。現代日本語の文字として正式に存在するのはウからアへの変化「ゥア」で発音するワWaと、ウからオへの変化「ゥオ」で発音するヲWoだけだが、外来語が多くなった今では日本人もWiとWeを難なく発音している。
Uは内向する意識を作り出す。Wはその内向する意識が一気に解けるためワクワク、ワイワイ、フワフワのように、外に向かって膨らむ意識を喚起する。
まるで雲のように、ムクムクと湧き上がるような発音体感である。このため、Wは偶数拍に使われる擬態語では、Wは整然とした動きを攪乱する役割をする。ソワソワは気持ちが乱れて落ち着かない様子、シワシワは布や皮膚の表面の乱れた線を表す。フワフワも、気持ちや行動が定まらない様子に使われる。YもWも母音変化で出す音なので、やわらかさをもっているのだが、一見似ているようで、まったく違う。
Yはやわらぎと揺らぎ、Wは膨張と攪乱の語感なのだ。ソヨソヨとソワソワを比べてみれば、その違いは一目瞭然である。擬態語における発音体感の正確な使われ方にちょっと驚きませんか?そして何よりも注目すべきはソヨソヨとソワソワを、誰に意味も教わらずとも使い分けてきた、私たち自身なのじゃないだろうか。
YとW、実は子音でありながら子音ではない。これが今回得た発見です。
母音を重ねて使っている内に誕生した新たな言語、そんな印象を受けます。この2重母音という概念を抑えておく事が以後の日本語の解明に一役買う予感があります。
シリーズ「日本人は、なにを信じるのか?」~第3回:神仏と共に生きた時代
シリーズ「日本人は、なにを信じるのか?」~第3回:神仏と共に生きた時代

<宇佐神宮 リンクより引用>
今回「日本人は何を信じるのか?」シリーズの第3回目の記事ですが、若干の軌道修正を行います。
この間、日本人は宗教心のない特殊な民族であるということを軸にシリーズを進めてきたのですが、仲間と議論や調査を重ねていくうちに、「本当に日本人は宗教心が薄いのか?」という疑問が生じました。
というのも、日本全国どこに行っても神社や寺が数え切れないほど建立しているのは疑いない事実ですし、たとえそれらが支配階級主導で建てられたとしても、受け入れてきた日本人がいたからこそ、現在も存在できていると捉えることもできるからです。
現代人のアンケートだけをもとに、『日本人は宗教心がない』と断定してしまうのは、あまりにも浅い分析なのではないか  あるいは、日本人の心の奥底には、日本の長い歴史の中で培われた私達が見落としているなんらかの構造が横たわっているのではないか
あるいは、日本人の心の奥底には、日本の長い歴史の中で培われた私達が見落としているなんらかの構造が横たわっているのではないか 
という期待感をもって、以下のようにシリーズの記事構成を見直します ![]()
1.プロローグ
2.現代日本人の宗教観
3.神仏と共に生きた時代  今回の記事
今回の記事
4.儒教の影響
5.近世における宗教観
6.葬式仏教とは
7.神話から出発した日本の近代
8.日本人と自然(宗教)
9.精霊信仰とは
10.祖霊信仰とは
11.共同体と信仰
12.日本人は何を信じるのか?(日本人の可能性)
今回は、第3回目の記事からスタートしますが、まずは日本人の宗教感について学んでいこうという主旨で、題して「神仏と共に生きた時代」を扱います 
当ブログでもなんどか扱われたことがありますが、古代日本人は、自然現象や山川草木など、あらゆるものの中に精霊=神を見出していました。電気やTVなどがない時代ですから、それこそ天気や季節の移り変わりの目安を自然のなかから読み取ってきたのです。
農耕が伝来する前の生産様式である採取狩猟はいうまでもなく、弥生以降に農耕生産が主要な生産手段であった日本人にとっては、自然現象や山川草木が生活に密着しているのです。つまり、精霊=神は西欧風の擬人化された存在ではなく、身近な存在として意識されていたのです。また、共同体社会であった古代日本の社会においては、自然万物を神として敬うことで、農作物の豊穣を祈り、仲間との結束をはかってきたのだと考えられます。
<リンクより引用>
<リンクより引用>
それら自然、信仰、時間に対する日本人独自の感性は、現在もなお、日本の伝統的なしきたりや年中行事の根底に息づいていると見てとることができます。
(ex.彼岸、お盆、正月、節分、例大祭、新嘗祭)
八百万の神とは、どのような意味があるのでしょうか?
以下『日本人のしきたり 飯倉晴武 青春出版社』より引用します。
◆八百万の神
日本人はキリスト教やイスラム教のように唯一絶対の神ではなく、自然万物のあらゆるものに神を見いだしてきました。
俗に八百万の神というように、太陽、月、星、風、雷といった神もいれば、土地、田、山、川、石などに、また、家の台所、かまど、便所などにも神がおり、さらには馬、犬などの動物、松、竹などの植物にも神が宿るというように、多くの神々があまねく存在する点に特色があります。
「八百万」とは非常に数が多いことの形容ですが、この言葉はすでに日本最古の歴史書である『古事記』(上巻)のなかに見られます。天照大神が、弟のスサノウノミコトのあまりの乱暴さに腹を立てて天の岩戸に隠れてしまったので、困った神々が「八百万の神、天の河原に神集ひ集ひて・・・」という記述がそれです。
そもそも太古の日本では、あらゆる自然物に霊魂を認め、それを畏怖し、崇拝するアニミズムと呼ばれる原始信仰が生まれます。やがて、卑弥呼に代表される巫女などが、神のご神託を受けて物事を決めるシャーマニズムにて発展していきました。
一方で、狩猟採集生活をしていた日本人も、米の伝来にともなって農耕生活へと変わっていきます。農耕生活はとりわけ、人間の力の及ばない自然現象に大きく左右されます。天候不順や自然災害による不作はまさに死活問題で、それらを神の怒りと考えたのも無理からぬことでした。そこから、あらゆる自然の営みに神を見いだし、崇める傾向がさらに強まっていったと思われます。
また、農耕社会で定住生活が始まると、土地に対する信仰も強まっていきます。自分たちが生まれた土地を守ってくれる神を「産土神」と崇め、産土神を祀る社を作るようになっていきました。さらに古来の祖先信仰も合わさって、日本ならではの神々への信仰が根づいていったと考えられます。
◆神と仏
現代の日本には神道と仏教が共存していて、結婚などの慶事のときは神式で、葬式など弔時のときは仏式でというように、自然に両者の使い分けができています。
もともと神道は、太古から日本固有の神への信仰に由来するのに対して、仏教は大陸から伝来した宗教です。また、神道は神話に登場してくる神々のように、地縁・血縁などで結ばれた共同体を守ることを目的としているのに対して、仏教はおもに個人の安心立命や魂の救済、国家鎮護を求める点で根本的に違っています。
仏教は西暦五三八年、日本に伝来したといわれます。仏教は豪族たちを中心に、少しずつ日本に広まり、聖徳太子以降、国家に守られる形で急速に浸透していきます。
しかし、そんななかでも、日本古来の神への信仰は廃れることなく、仏教と共存していったのです。むしろ奈良時代以降、神仏は本来同じものであるとする「神仏習合」や、神は仏が仮に形を変えてこの世に現れたものとする「本地垂迹説」など、両者の融合を図る思想が生まれていきます。
さらに平安時代には、それまで国家鎮護が主だった仏教が、しだいに庶民にも根づき、神も仏を尊ぶという、日本ならではの信仰が形成されていきました。
明治政府の神仏分離令で、この神仏混交の思想は禁止されますが、いまなお神への信仰と仏教が融合した習俗は多く残っています。
例えば、お彼岸やお盆はもともとは仏教の行事ですが、そこに日本古来の祖先神への信仰が結びついて生まれた習慣です。
◆氏神と鎮守
いまも昔も、人間は困ったことや追い詰められた状態になると、神に助けを求めたりします。特に地縁や血縁が大事にされた時代は、一番身近にいつその土地の神様に願いを託しました。それが氏神であり、鎮守の神でした。
そもそも氏神は、その地域の豪族である氏一族の祖先を祭った守護神でしたが、平安時代以降、一般庶民にも浸透していき、広くその地域を守る神様となって崇められるようになりました。
現在でも行われている子どものお宮参りは、本来はこの氏神にお参りして、その土地の一員になることを認めてもらう儀式だったのです。
やがて平安時代以降、武家社会が形成されると、氏族社会が崩壊して、氏神信仰も薄らぎます。それに代わり、貴族や社寺の私的な領地である荘園制度が確立されていきました。
そこで新たに荘園領主たちは、荘園を鎮護してもらう目的で、その土地の守護神を祀るようになります。これが鎮守と呼ばれるものです。そして、それまでの氏神でも、鎮守の神を祀るようになりました。
その後、江戸時代にはふたたび氏神信仰がさかんになります。こうした変遷を繰り返すなかで、両者は地域を守る神として、庶民の間にも根付いていきました。
言われてみれば、上記の意識や宗教観は、私たちの生活に見事に溶け込んでいます ![]()
しかし、日本人の生活にこれだけ密着している宗教にもかかわらず、外国人に「あなたはどんな宗教を信仰しているの?」とか「日本人は宗教心があるのか?」と問われた際に、明確に答えられる人はそんなに多くないのではないでしょうか。そこで、そのような日本人の意識をうまく表現している書籍がありましたので、紹介します。
以下、「日本人はなぜ無宗教なのか 阿満利麿 ちくま書房」より抜粋引用します。
●神仏とともに生きた時代
(前略)
この点、私はかねてから、「自然宗教」と「創唱宗教」という区別が日本人の宗教心を分析する上では有効だと考えている。「創唱宗教」とは、特定の人物が特定の教義を唱えてそれを信じる人たちがいる宗教のことである。教祖と教典、それに教団の三者によって成り立っている宗教といいかえてよい。代表的な例は、キリスト教や仏教、イスラム教であり、いわゆる新興宗教もその類に属する。これに対して「自然宗教」とは文字通り、いつ、だれによって始められたかも分からない、自然発生的な宗教のことであり、「創唱宗教」のような教祖や教典、教団をもたない。「自然宗教」というと、しばしば大自然を信仰対象とする宗教と誤解されがちだが、そうではない。あくまでも「創唱宗教」に比べての用語であり、その発生が自然的で特定の教祖によるものではないということである。あくまでも自然に発生し、無意識に先祖たちによって受け継がれ、今に続いてきた宗教のことである。
(中略)
ここでいう「無宗教」とは、「創唱宗教」に対する無関心という意味であることをもう一度確認しておこう。「無宗教」だからといって宗教心がないわけではないし、ましてや欧米人がいう「無神論者」というわけではない。あくまでも「創唱宗教」に対して無関心だということであり、多くの場合、熱心な「自然宗教」の信奉者であることはすでに見た通りである。
では、どのようにして「創唱宗教」に対する関心を失っていったのであろうか。話は、日常生活のすべてが神仏とともに営まれていた中世にさかのぼる。
中世の定義は難しいが、さしあたり三つのことが信じられていた時代だといって間違いはないだろう。一つは、神仏の存在が文字通り信じられていたこと。第二は、仏教とともにもたらされたインド人の世界観である六道輪廻、つまりあらゆる生き物は地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天、の六つの世界を経巡り続けるということを信じていたこと。前世や来世の存在と生まれ変わりが信じられていたのである。そして第三に、死後、地獄や餓鬼、畜生といった世界に落ちないように、死後の世界の救済が切実に求められていたこと、この三者が一体となって信じられていた時代が日本の中世なのである。
中世の代表的な宗教家・親鸞を例にとってみよう。親鸞が当時革命的な念仏思想を説いていた法然の弟子になったのは、死後地獄に堕ちないようにするにはどうしたらよいのか、という悩みからであった。
当時の多くの人々が出家して僧侶になった理由の一つは、六道輪廻の恐怖から逃れるためであった。それには仏になるのが最上の解決方法であった。仏とは、最高の知恵を身につけることによって二度と六道を輪廻することがない存在にほかならない。そして出家して僧侶となることは、その仏になる道をひた走ることを意味した。
だが、仏になるための修行をどうしてもやり通すことができないという深刻な問題が自覚されはじめる。煩悩、つまり自分で自分をコントロールしきれない、根の深い欲望が真正面から問題とされるようになってきた。親鸞の悩みはまさに自分のなかに深く巣くう煩悩の克服に無力であるところにあった。そうした悩みのなかでは、いかにいわばカリキュラム通りの修行を重ねてもなんの効果もなく徒労感だけが残る。
親鸞が具体的にどのような欲望にさいなまれたのかは、定かではない。だが、このままでは死後は地獄に堕ちるしかないというせっぱ詰まった思いにとりつかれていたことだけは確かである。その苦しみを解決するために、京都の町中の六角堂にこもった。観音のお告げを受けるためである。
当時は、人々は解決が容易ではない問題にぶつかると、しばしば霊験あらたかな神仏のお告げを求めて社寺にこもることが習わしなのであった。そこで人々は、夢のなかで神仏のお告げに出会うことができたのである。夢は、中世人にとっては、神仏に出会うための不可欠の通路なのであった。神仏は、夢を通して人々にその意志をあらわすと、信じられていた。
親鸞の場合も六角堂にこもり始めて九五日目の暁に、観音のお告げを受けることができた。そのお告げをきっかけに、親鸞は、死後の救済を与えてくれる人として法然を訪ねるのである。
(中略)
六道輪廻の苦しみから解放されたい!そのための有益な方法ならばその実践には惜しむところはない。それが中世人の大方の生き方なのであった。そこでは宗教に無関心な生活などありえなかった。
(後略)
ここまで見てきたように、日本人は無宗教どころか、むしろ宗教と深いかかわりがあることが読み解けます。
しかし、日本人の宗教観が、西欧の宗教(キリスト教やイスラム教など)と大きく異なる点のは、誰かがつくった宗教を信仰しているのではなく、自然発生的に生まれた宗教を信仰しているという点です。だからこそ、生活に溶け込んでいるから、なかなか見えてこないのかもしれません ![]()
次回は、親孝行という言葉に代表されるように、現在も生活の中に浸透している「儒教の影響」について扱います。お楽しみに 
シリーズ「日本人はなにを信じるのか」~4.儒教の影響
シリーズ「日本人はなにを信じるのか」~4.儒教の影響
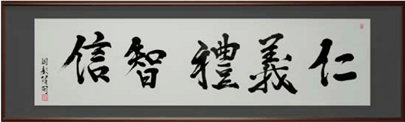
株式会社ココシスさんよりお借りしました
日本人の信仰心の背景に迫る、シリーズ「日本人は何を信じるのか」
今回は、前回紹介した信心深い平安の頃までの日本人が、武家社会となった中世になってどのように変化していったのか、探ってみたいと思います。
信仰心の深かった日本人が、なぜ現代では無宗教などと言われるようになったのか?
本当に信仰心は無くなったのか?
そのきっかけが中世にありそうです。
まずは、前回に引き続き、「日本人はなぜ無宗教なのか」阿満利麿著(ちくま書房) よりの引用です。
【2】儒教の登場
~前略~
南北朝時代と室町時代の武家の家訓を調べた研究によると、神仏を尊崇することを強くすすめる武家たちの家訓に、このころから、儒教の徳目があらたに加わってくるようになる。はじめは、仁義礼智信という徳目を守ることが神仏への信仰とならんで強調されているけれども、やがて、神仏がこの世に姿をあらわすのも、儒教の教え、つまり仁義礼智信を人々に実践させるためであり、一度として、仏の前で手を合わせたり神社の社殿にぬかずくことをしていなくても、こうした儒教の教えを守っているかぎり、神仏もその人間を救うのだと教えるようになってくる。だから神仏をいわば名指しで頼むのは、死後極楽に生まれるようにと祈るときだけであり、平生は儒教が理想とする道徳を実践していれば十分だという主張になったのである(柏原祐泉「武家家訓における儒仏受容の過程」)
哲学ニュースnwkさんよりお借りしました
死後、地獄に堕ちないための神仏への信心がこの世での生活目標であった時代に比べると、この儒教の教えを第一とする生き方は現世中心に大きく変化したということになろう。
つまり、仁義礼智信という人間関係の理想的なありようを追求することになったのであり、神仏を頼むという生き方はいわばつけたりになった、といってもよい。あるいは、宗教は個人の私的な頼み事となってしまったということである。
儒教は、もともと、士太夫とよばれた中国社会の支配階級に属する人々の政治哲学であり、彼らの処世術からはじまった。したがって、儒教でははじめから現実社会における人間の生き方、身の処し方に関心が集中することになり、死後の救済は、ほとんど関心の埒外となる。このような儒教が日本でも勢いをもちはじめたということは、それだけ人々の関心が現世中心になりだしたということにほかならない。
さらにいえば、中世も時代を経て、生産力が次第に上昇をはじめ、人々が現実生活に自信をもちはじめるようになるにしたがい、あるべき主従関係、夫婦関係、親子関係、朋友関係など、人間のあり方や生き方が新たに求められ、全体として社会の新秩序が求められるようになってきた。そしてそうした変化のなかでは、死後の救済祈願は、片隅に追い込まれる一方となってきたのである。
結論だけをいえば、儒教が専門家の間をこえて武家社会や豪商・豪農クラスに広がり始めたことが、「無宗教」、つまり特定の宗派に無関心となる歴史のはじまりでもあるのだ。
こうした傾向をいっそう助長したのが、これからのべる近世の「浮き世」意識であろう。

はないかださんよりお借りしました
中世16世紀の室町時代に儒教が伝播してから、武家の教えを始めとして、神仏への信仰に加えて、徳目を守ることが意識され出します。
そのうち、信仰行為よりも日常の徳目(道徳)を守っていくことが、信心を表すという解釈となり、その道徳意識が第一課題となっていく。
そして、特定の宗教への意識は弱まり、宗教に拘らない意識が形成されていくことになります。
このような意識の変化が、特定の宗教に拘らない日本人を作り出していったのではないでしょうか。
信仰心は無くなっていないが、その信仰的行為が日常の生活に深く溶け込んでいった。だから信仰心が、道徳という言葉に置き換わり、例えば「しきたり」などとして後世まで信仰行為の名残が残っていくことになります。
このように、日本人の信仰心は生活に深く溶け込むことにより、見えにくくなっているのではないでしょうか。
さて、次回はさらに近世に焦点を当てて、日本人の信仰心に迫っていきます。
シリーズ「日本人はなにを信じるのか」~4.儒教の影響
シリーズ「日本人はなにを信じるのか」~4.儒教の影響
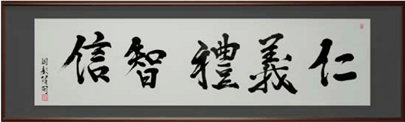
株式会社ココシスさんよりお借りしました
日本人の信仰心の背景に迫る、シリーズ「日本人は何を信じるのか」
今回は、前回紹介した信心深い平安の頃までの日本人が、武家社会となった中世になってどのように変化していったのか、探ってみたいと思います。
信仰心の深かった日本人が、なぜ現代では無宗教などと言われるようになったのか?
本当に信仰心は無くなったのか?
そのきっかけが中世にありそうです。
まずは、前回に引き続き、「日本人はなぜ無宗教なのか」阿満利麿著(ちくま書房) よりの引用です。
【2】儒教の登場
~前略~
南北朝時代と室町時代の武家の家訓を調べた研究によると、神仏を尊崇することを強くすすめる武家たちの家訓に、このころから、儒教の徳目があらたに加わってくるようになる。はじめは、仁義礼智信という徳目を守ることが神仏への信仰とならんで強調されているけれども、やがて、神仏がこの世に姿をあらわすのも、儒教の教え、つまり仁義礼智信を人々に実践させるためであり、一度として、仏の前で手を合わせたり神社の社殿にぬかずくことをしていなくても、こうした儒教の教えを守っているかぎり、神仏もその人間を救うのだと教えるようになってくる。だから神仏をいわば名指しで頼むのは、死後極楽に生まれるようにと祈るときだけであり、平生は儒教が理想とする道徳を実践していれば十分だという主張になったのである(柏原祐泉「武家家訓における儒仏受容の過程」)
哲学ニュースnwkさんよりお借りしました
死後、地獄に堕ちないための神仏への信心がこの世での生活目標であった時代に比べると、この儒教の教えを第一とする生き方は現世中心に大きく変化したということになろう。
つまり、仁義礼智信という人間関係の理想的なありようを追求することになったのであり、神仏を頼むという生き方はいわばつけたりになった、といってもよい。あるいは、宗教は個人の私的な頼み事となってしまったということである。
儒教は、もともと、士太夫とよばれた中国社会の支配階級に属する人々の政治哲学であり、彼らの処世術からはじまった。したがって、儒教でははじめから現実社会における人間の生き方、身の処し方に関心が集中することになり、死後の救済は、ほとんど関心の埒外となる。このような儒教が日本でも勢いをもちはじめたということは、それだけ人々の関心が現世中心になりだしたということにほかならない。
さらにいえば、中世も時代を経て、生産力が次第に上昇をはじめ、人々が現実生活に自信をもちはじめるようになるにしたがい、あるべき主従関係、夫婦関係、親子関係、朋友関係など、人間のあり方や生き方が新たに求められ、全体として社会の新秩序が求められるようになってきた。そしてそうした変化のなかでは、死後の救済祈願は、片隅に追い込まれる一方となってきたのである。
結論だけをいえば、儒教が専門家の間をこえて武家社会や豪商・豪農クラスに広がり始めたことが、「無宗教」、つまり特定の宗派に無関心となる歴史のはじまりでもあるのだ。
こうした傾向をいっそう助長したのが、これからのべる近世の「浮き世」意識であろう。

はないかださんよりお借りしました
中世16世紀の室町時代に儒教が伝播してから、武家の教えを始めとして、神仏への信仰に加えて、徳目を守ることが意識され出します。
そのうち、信仰行為よりも日常の徳目(道徳)を守っていくことが、信心を表すという解釈となり、その道徳意識が第一課題となっていく。
そして、特定の宗教への意識は弱まり、宗教に拘らない意識が形成されていくことになります。
このような意識の変化が、特定の宗教に拘らない日本人を作り出していったのではないでしょうか。
信仰心は無くなっていないが、その信仰的行為が日常の生活に深く溶け込んでいった。だから信仰心が、道徳という言葉に置き換わり、例えば「しきたり」などとして後世まで信仰行為の名残が残っていくことになります。
このように、日本人の信仰心は生活に深く溶け込むことにより、見えにくくなっているのではないでしょうか。
さて、次回はさらに近世に焦点を当てて、日本人の信仰心に迫っていきます。
始原の言語・日本語の可能性~(4)
始原の言語・日本語の可能性~(4) 実体(対象)と発音体感の一致 ラ行(R)は哲学の響き/ナ行(N)は抱擁の感覚/ハ行(H)は熱さをあらわす
日本語は、実体(対象)と発音が一致した美しい言語。その音を発する時の口腔内感覚→発音体感が、それが指し示す対象(実態)の様子と密接に関わっている。
前々回、カ行、サ行、タ行の発音体感、リンク
そして前回は、ヤ行、ワの発音体感をお伝えしました。リンク
今回は、ラ行、ナ行、ハ行を扱います。もう飽きてしまいましたか?そんなことは言わせません。いずれも、やはり独特の音感を持っており、対象の様子(または、主体の状況)と見事に連関しています。今回もフムフムと言って頂けるのではないかと思います。
以下、囲み部分は、黒川伊保子氏「怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか」からの引用です。
リズムの「り」、理の「り」、命令に「れい」。Rは確かに、繰り返す様子→自然法則→規則と繋がっていっているようですね。次は、50音の中盤に戻って、ナ行です。
【抱擁の音 N】 な、に、ぬ、ね、の
N音は、鼻腔を響かせて出す音(鼻音系)である。上あごに舌のほぼ全体を密着させ、鼻腔音を出しつつ舌をはがすことによって発音する。上あごと舌の密着感、頭蓋内にこもって響く音のため、非常に私的な、内向的なイメージになる。また、頭蓋内にこもる鼻音は、息を使って出す他の音に比べてスピード感がないため、遅い、停留のクオリアをもつ。
(中略)
鼻音(な、に、に、ね、の、ん)は、頭蓋の真ん中、鼻腔に響くので、自分の最も内側にある音だ。その上、上あごに舌を密着させる感じは、誰かにしっかり肌を密着されて抱擁されている心地よさを誘発する。(中略)
この赤ん坊のおしゃぶりは、擬似おっぱいではなく、擬似抱擁だ。お腹の空いた赤ん坊におしゃぶりをくわえさせても怒って泣くだけだが、おしゃぶりをくわえている赤ん坊は、抱っこをせがむ回数が明らかに少ない。このように、N音の発音構造の一つ、上あごと舌の密着は、抱擁を感じさせる。したがってN音は、自分で自分を抱擁する癒しの音なのである。(中略)
母の素肌の抱擁に代替したN音は、非常に私的な感情も喚起する。ナナコという名前にどこか家庭的な印象を受けるのは、松嶋菜々子さんの影響ではない。そもそも実際の松嶋さんはバリバリ外で働いている。きらめく大スターでもある。なのに常に傍にいる「お姉さん」のイメージが消えなかった(これからは「お母さん」になってゆくのだと思うけれど・・・・)。ナナコさん、ナエさん、キリコさん、キョウコさんでは前者のほうがどこかおしとやかに感じられないだろうか。
密着:ナメナメ(幼児語)、ねえねえ(呼びかけ)
粘性:ねとねと、ぬるぬる、
癒し:にこにこ、ニャーニャー、
遅さ:のろのろ、のそのそ、
【体温の熱さ H】 は、ひ、ふ、へ、ほ
H音は、舌の付け根周辺をほっこりと開け、器官から出てくる息をブレイクさせたり擦ったりせずに、そのまま一気に口元まで運ぶことで出す音である。同じ要領でも、息をゆっくりと運ぶと音はでない。ある程度の量の息を一気に出すことで喉壁と息の摩擦が起こり、音が発生する。(中略)
物理抵抗を受けない息は、器官の体温を温存したまま外へ出てくるので、温かさの質を持っている。この温かさの質は、後続の母音によって色合いが違っている。器官からの息をそのまま口元まで一気に運ぶHaの温かさは、かじかんだ手を温められるほどだ。器官からの息を、喉奥の大きな空洞でやんわりと包んで外に出すHOも、口元の温度が高い音になる。
これに比べて、Hi、Huは、口元の温度が低い。この2音を「温かい」と言われると首を傾ける方も多いだろう。Hiは氷にも当てあられる音(氷雨、氷室)であり、フーフーは熱いものを覚ます息の音。「冷たい」というご叱責さえ受けることもある。
しかしながら、このHi、Huは、熱いくらいのサブリミナル・インプレッションを持っている。実は、口腔空間を小さく使う母音I、Uのおかげで、喉まで体温を温存してやってきた息の熱は、喉や口腔中空にぶつかり、ここに熱さを感じさせている。喉や口腔に熱を与えることによってエネルギーを消失した息は、口元に出てきたときには、もう冷たいのである。
口元の息がクールなので顕在意識は気づかないが、喉に直接与えられるHiは、ハ行の中で最も熱い。というより、Iの鋭さの印象が効いているので、痛いほどに熱い、と言う方が正しいかもしれない。日(Hi)、火(Hi)は、その素直な表出語である。
温かさ:ホカホカ、ホクホク、フウフウ、ヒリヒリ、
開放感:ホっとする、フワフワ、ほわほわ
解けるイメージ:ヒラヒラ、ハラハラ、ホロホロ、
以上、概ね全ての子音を扱いました。詳しく言うと、濁音、半濁音などを扱っていませんが、またの機会にとっておきましょう。
ここに上げられた、発音体感と対象(実体)の精密な対応関係は、(必ずしも日本語だけのものではありませんが)、擬音語・擬態語などに特に特徴的に見られるように、日本語にはその関係が、特に鮮明に豊かに存在する(残存している)ことが分かります。
日本語が、実感・潜在思念を観念にがっちりと結びつけた豊かな言語であることが分かり、日本語の可能性を改めて認識できますね。次回は、いよいよ、日本語は「母音言語」といわれる、その「母音(アイウエオ)」を扱って行きます。



