したいという」静かな闘志、それが未知収束
したいという」静かな闘志、それが未知収束
現在人の闘争とは何か?⇒「対象の全容を少しでも解明したいという」静かな闘志が戦うモチベーションに繋がる。それが未知収束の心根にある。
哺乳類はオスメスの性差をさらに強化することで進化してきた。人類はその進化の最終位置にあり、当然オスは闘争に特化し、メスは生殖=性に特化した。ただ、人類のオスの闘争は他の哺乳類が成した縄張り闘争発の性闘争とは異なる。これが何なのかをこの間ずっと考えていたが、少し見えた処があったので記事にしておきたい。将棋の世界は勝負が常にあり、まさに文字通り闘争の世界である。そこの第一人者に長く存在している羽生善治の言葉がある。闘争とは何かがその中にあるのではないか、探してみた。
羽生善治著の「闘う頭脳」という著書から紹介してみたい。対談形式でインタビュアーが羽生さんは目標という事をどのように考えておられますかという平板な質問に対して答えている、その中に現れた。
「ビジネスの世界の方々は目標を設定するところから始まるのかも知れませんが、私の場合は、何かと戦うという個別の目標を立てて進んでは来なかったんです。特に棋戦―直近でいうと4月からの名人戦とか、6月からの棋聖戦―をどうやって勝つか、というような目標設定はあまりしていないんです。スケジュール調整は半年先くらいまで進めていきますが、将棋の戦術的な面は日進月歩、1週間単位で更新されて進化していきますから、数ヶ月先の対局の事をいま考えても仕方がない。もちろん将棋の戦術については気にしていますし、常に新しいものを探しています。そういう日常の営みの中で少しずつ考えていくというところですね。数ヶ月後の名人戦を「こう戦おう」といま戦術を考えても、そのまま戦ってうまくいく事はまずありません。ですから今年はこのタイトルを獲ろう、とか誰に勝とう、という事はまずありません。ですから、今年はこのタイトルを獲ろう、とか誰に勝とうとかというような目標の立て方は私の場合はしないですね。
(中略)
とは言え、30年ずっとプロ棋士を続けてきたわけで、その理由がなにかと考えてみますと「将棋の全容を少しでも解明したい」という静かな気持ちはあります。あえて言えば、これが棋士を続けるモチベーションになっているのかも知れません。将棋の解明が難しいということはよく認識しています。将棋の局面の可能性は10の約220乗通りあるといわれています。そのうち、この目で見ることができるのは0.1%もないでしょう。それでも少なくとも自分が対した局面については、できる範囲で突き詰めたという気持ちはあります。対局で未知の局面に出会った時は、感想戦(対局のあと、対戦相手と一局を振り返り、双方の指し手を検討する事)で、ある程度の結論を出さないと気分が悪い。若いときからそれは変わりませんね。一つの局面を考える事で、新たな問題が出てきて、さらにその対策を考え、そこに次ぎの対抗策が・・・、とそんな事を毎日考えながら、30年が経ったという感じです。」
羽生さんの言葉は柔らかく、好奇心とは追求心とか探究心などという言葉に変える事ができるかもしれないが、あえて彼の言葉をそのまま使いたい。
★「将棋の全容を少しでも解明したい」という静かな気持ちはあります。
★対局で未知の局面に出会った時は、感想戦で、ある程度の結論を出さないと気分が悪い。若いときからそれは変わりませんね。
★一つの局面を考える事で、新たな問題が出てきて、さらにその対策を考え、そこに次ぎの対抗策が・・・、とそんな事を毎日考えながら、30年が経った。
羽生氏の闘争とは「対象の全容を少しでも解明したい、掴み取りたい」という意識であり、相手と闘って勝つというのは2の次なのだ。この心のありよう、ワクワク感や子供時代と変わらない意識、が実に様々な世の追求者と一致する。言い換えれば赤ん坊の追求とはまさにそれで、世の中に生まれ出て、次々と登場する事象や対象を“少しでも解明したい”という気持ちでほぼ無意識に毎日なんで、なぜを繰り返す。
以前、実現塾で語られたくだりを思い出す。
赤ん坊は100パーセントが追求者、皆一度は追求者であった。大人になって追求心が曇り、ワクワク感や未知追求への意欲が減じていくが、稀にわずか2,3%の確率で、赤ん坊の頃の追求心を大人まで延長した人が居る。それが成功者や事業の勝利者に多いのは彼らが真の追求者であったからだ。凡人は前例のない難しい仕事や難課題を向えると頭を抱えるが、真の追求者は未知課題を向えると活き活きと逆に闘争心が湧いてくる。羽生氏が言うように新たな問題が出て、さらにその対策を考え、そこに次の対抗策が・・・と次々と向っていく。
人類のオスの闘争とは何か、未知なるものへの挑戦である。現代的な課題に置き換えると、既に回りには未知なるものは山ほどある。真の追求者にとっては宝物の中で生活しているようなものだ。それを宝物と思えるかただの石ころと思うかはその人の闘争心にかかっている。
未知収束の心根とはこのような処ではないだろうか?
【新説提案】現世人類の最古の産業は漁労ではないか?
【新説提案】現世人類の最古の産業は漁労ではないか?
年末最後の記事は漁労文化について書いてみたい。
人類の最初の産業は何か?誰もが農業、或いは狩猟と答えるだろう。
しかし、その可能性は漁労が最も高いのではないかと考える。もちろん旧石器時代に洞窟に隠れ住み、夜な夜な暗闇をに死肉を漁った時代は捕食の為とは言えるが産業とは呼べない。弓矢や投てきで獲物を確保したのは洞窟から出る事のできた1万年前~1万5千年前。農業に至ってはどれだけ遡ってもせいぜい1万年前だ。
しかし、漁労の可能性は遺物だけを見ても3万年前に遡る。かつては日本の南の島で2万3千年前の釣り針の遺跡が最古だったが、昨年韓国で2万9千年前の投網の重りの遺跡が出てきた。いったいいつまで遡るかであるが、私見ではあるがおそらく5万年前まで遡るのではないかと考える。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4つの根拠を考えてみた。
最初は人類の発祥の地、アジア説。現世人類(ホモサピエンス)はアフリカ大陸で誕生してその後5万年前からユーラシアに広がったという説が最近崩れている。おそらく、6万年前前後まで大陸として存在したスンダランドから現世人類は誕生し、広がったのではないかと思われる。スンダランドはわずか100mの海面上昇で姿を消すような平地であり、海の中に様々な島が点在する現在のインドネシアのような地域が広域にあったものと思われる。なおかつ、その島の中には肉食動物も少なく、人類にとっては外敵の少ない楽園だった可能性がある。その中で最大限活用できたのが海の資源。釣り針、投網、浅瀬での貝などの採取など、栄養価が豊富な海辺を生活の拠点としていた可能性は高い。
もう一つの理由が人類の大移動である。まだ定住をしていない人類は季節や気候で居住地を移動しながら生活していたと考えられる。元々洞窟での定住を強いられていた人類だが、船の技術を身に着けることで海洋を海岸線伝いで移動することが可能になった。さらに船の技術が仮になくても海岸線の移動は内陸に比べてはるかに安全で昼間の移動を可能にする。既に5万年前にはオーストラリア含む各地に広がっていた人類はこの海岸線を伝って移動する手段、技術を最も最初に獲得したのではないか?獲得したが故に広域に広がった。そういう意味では現世人類の最初の技術は船舶であり、漁労の技術を駆使して各地で生存した。
3つめの理由が脳容量である。ホモサピエンスは1350ccとネアンデルタール人の1450ccに比べて100cc少ない。なおかつ体格も華奢で肉体的機能においてネアンデルタール人に劣っている。ネアンデルタール人がヨーロッパで主に活動しその生産の中心が狩猟であった事は言われているが、脳が大きく体格がしっかりしているネアンデルタールに比べてなぜ現世人類がそこまで大きくならなかったのか。その理由が漁労ではないかと推定した。つまり、脳容量の100ccの差は主に運動機能を司る小脳であり、屈強な肉体や体力をそれほど使わない漁労を中心にしていたが故に華奢で脳容量を限界まで大きくする必要はなかった。逆に脳容量は100cc小さいが、ものを考えたり追求する知的脳はネアンデルタールもホモサピエンスもほぼ同容量である。また魚の栄養は血液や脳に非常によく、人類のその後の進化を後押しした可能性もある。※最近の報告で小脳はホモサピエンスの方が大きいという事実もありましたのでこの説は追求が必要
最後の理由が縄文文明。縄文文明は4大文明に先駆けて登場した世界最古の文明という説もある。また、縄文文明は最後まで農業を取り入れなかった採取・漁労文明である。その後の日本の歴史は農業中心で成立した世界の他のどの文明とも異なる独自性をもっており、その一つに漁労文明を最大限まで拡大した縄文時代にあったのではないかと見る。現在の日本人の寿命が世界最長であるのと関りがあるかどうか明らかではないが、列島の四週が海で囲まれ、なおかつ海洋資源豊富な温暖海流が流れる日本の食資源の優位性はつい最近まで漁労にあった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人類が文明を生み出し、小麦やコメの生産を拡大する中で漁業の地位はどんどん相対的に小さくなってきたが、それは貯蓄が効き、生産をコントロールし、支配しやすいのが農業であったという事で、逆に言えば漁業は経済ベースに乗らない支配しにくい生産故に文明時代以降大きく変化してこなかっただけである。
その事と人類誕生、拡大の最大の立役者が漁労であったという事は連関しない。人類は漁労がなければ今日のように進化、発展はしてないかもしれない。それくらい、漁労は人類の進化にとって注目すべき最初の産業ではないだろうか。
以下、昨年発表された「漁労の始まりがさらに古くなった」という記事を紹介。
【8月7日 AFP】韓国・江原道の旌善郡の洞窟で6月に発掘された、漁網用の重しである石錘14個が、約2万9000年前のものと判明した。今回の発見は、洗練された技術を用いた漁がこれまで考えられていたよりもはるかに古くから行われていたことを示唆している。 延世大学博物館の韓昌均(ハン・チャンギュン氏はAFPの取材に対し、放射性炭素年代測定の結果、6月に見つかった石灰岩製の石錘によって「網を用いた漁労の歴史がこれまでより1万9000年もさかのぼる」ことになったと語った。
石錘はこれまでも日本の福井県と韓国の清州市で発掘されており、いずれも約1万年前の新石器時代のものとみられている。だが今回の発見は、後期旧石器時代でも人類は活発に漁労を営んでいたことを示唆するものだと、韓氏は指摘した。
14個の石錘はそれぞれ重さが14~52グラム、直径は37~56ミリ。韓氏は、漁網の端を結び付けるための溝が彫られており、浅瀬で小魚を獲るために用いられたと説明している。石錘が今回発見されるまでは、南日本の島で見つかった、約2万3000年前に巻き貝の殻で作られた釣り針が人類最古の漁具とされていた。(c)AFP
論って本当?
論って本当?

>次回は、水野家族論の紹介を通じて、縄文集落の有り様をさらに解明していきましょう!<
学者による集落論第2回【縄文の集団に学ぶ~その7】和島家族論って本当?
というさーねさんからのバトンを受け、今日は水野正好さんによる家族論を見ていきたいと思います。
前回の和島家族論を要約すれば、集団婚を経て対偶婚、家父長制大家族、そして小家族へ、というのが原初的な家族の大まかな発展の図式であり、そこには『家族・私有財産・国家の起源』におけるF・エンゲルスの、「血縁家族―プナルア家族―対偶婚家族―家父長制家族―一夫一婦制家族」という進化主義的家族観の強い影響がうかがえます。
一方、水野正好の家族・婚姻観の輪郭は、かれの最初の試論、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』の中にすでに明確な形、つまり、「二棟一家族論」と「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」として現れており、水野集落論全体を貫く基本的なモティーフとして今日へと続いています。
といったように水野氏は和島氏とは全く違ったアプローチでの「家族論」を展開しています。では、水野氏の提示する家族論の背景となるものはなんだったのか?について見ていきたいと思います。以下、要約版です。
1・縄文時代では集団婚が支配的であるとした和島に対し、同居制にもとづく、おそらくは単婚的な「小家族」がすでに登場をみていた可能性が指摘されています。しかも、「性別ないし機能集団」としての性格も考慮されています。この「小家族」は二軒の住居を一単位として成立するものであったことを、与助尾根集落におけるいわゆる「小群」の分析結果にもとづいて明らかにしたのです。
2・二軒を単位とする「小家族」のさらに上位には、埋葬・消費・政治の基本単位としての「家族」が存在していた可能性を、六軒の住居、つまり三小群から構成される「大群」との関連において指摘しました。
3・こうした三小家族―六軒の住居を包摂する「家族」すなわち「大群」は、東群と西群の併存現象にもうかがわれるように与助尾根では合計二群存在し、両群が一体となって「部族」としての「集落」全体を構成するという、立体的な縄文集落像を呈示したのです。
4・集落―大群―小群という重層的な群構成と部族―家族―(単婚?)小家族(または性別ないし機能集団)というレベルの異なる社会集団とを重ね合わせた水野は、続けて与助尾根における祭式を集落そのものに基盤を置く「広場祭式」、集落~大群間に基盤を置く「葬送祭式」、大群~小群間に基盤を置く「石柱・石棒・土偶祭式」の三類に分類し、全体として与助尾根の集落構造と宗教構造とを一体的に復元しようとしたのです。
5・住居出土の特殊な付属施設をもとに措定した大群~小群間に基盤を置く各祭式の性格を、狩猟神・祖家神にもとづく男性祭式としての石柱祭式、性神・成育神にもとづく同じく男性祭式としての石棒祭式、穀神・母神にもとづく女性祭式としての土偶祭式としてそれぞれ位置づけ、内容・形態を異にする以上の各祭式が各小群に分掌されるという、祭祀論に大きく立脚した特異な家族像を想定しています。これが「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」なのです。
与助尾根の集落分布から導き出された「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」ですが、この説は大きな問題を孕んでいるようです。水野家族論は1930年に宮坂英弌氏によって発掘された情報を基に1969年に纏められたものであるが、1998年に行われた試掘調査によって新たな遺構の分布が明らかになっている。
①1998年の調査で新たに発見された遺構を加えると39軒まで増加する。
②1930年の調査住居は実際の位置とズレがある。
③各住居の所属時期は、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在として見なしている。
④新たに発見された11軒のうち4軒は住居群の北側に分布し水野の言う集落全体(二大群12軒)―大群(三小群6軒)―小群(2軒一単位)という集落分割案では説明できない位置にある。
⑤東西に細長い台地に沿って弧状に広がると考えられていた与助尾根集落は、略環状、ないし北東に開く馬蹄形状を呈していた可能性が強く、新たな視点からの検討が必要。
これに対し、佐々木藤雄氏は次のような厳しい言葉を述べている。
>一体、どのような詭弁を弄すれば、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在例とみなすことができるのであろうか。想念の集落論と呼ばれる水野集落論の恣意性と主観性が、ここにはもっとも集約的な形で表出されていたといっても過言ではない。
与助尾根遺跡を舞台にした今回の試掘作業の結果は、歴史的な真理の究明よりも誤謬だらけの学史や定説の賛美と絶対化を繰り返す与助尾根集落論、否、日本考古学そのものへのまぎれもない鎮魂歌、レクイエムであったといわなければならない。<
与助尾根集落論―もう一つの「不都合な真実」より引用。
これまで「和島家族論」「水野家族論」を中心に学説を見る中で、様々な切り口からの仮説の提示こそあれど、どこか権威主義的・時には他者の意見を否定してでも自分の説を際立たせようといった手法まで垣間見られる。学者はその分野単独の知識としては長けている一方で、それ自体を職業にするが故にそういった偏った思考に陥りやすいといった構造にあることも否めないと感じた。
今後の追求ではそれ自体を生業としない、素人だからこそ見える視点・本当の事実はなんなのか?また、そこから見えてくる日本人のもつ特性・これからの可能性について調べていきたいと思います。
「日本人の‘考える力’を考える」シリーズを始めます。
「日本人の‘考える力’を考える」シリーズを始めます。
●難局を前にして、「日本人は自前でモノを考えだすのか?」
ご無沙汰してます、怒るでしかし~です。
私権統合の崩壊が、家庭、企業、国家、そして市場社会の崩壊現象として、顕在化しつつある。それに対して、人々は、遊び第1から課題収束へと転換し、そこかしこで、真面目な仕事話に取り組み、若者の多くが「社会の役に立つ」仕事を求めだしている状況は、縄文以来の伝統である共同体的精神をもった共同体企業の時代が到来したといっていいだろう。他方、政治レベルでみれば、官僚・マスコミの暴走に翻弄されているものの、支配力の低下は明白で、大衆自身による社会統合への兆しといえる現象も現れ始めている。(事業仕分け、名古屋市の地域委員制度等)
しかしながら、人々の秩序収束上の諸現象は、資格収束、目先収束や、安易な右傾化等、必ずしも健全な思考力を伴っているとはいい難い現象も多い。専ら、舶来信仰に依拠し、外来思想の受容を旨としてきた日本人は、果たして現代の難局を前に、「自前でモノを考えだすのか?」のだろうか。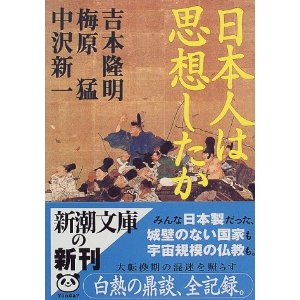
写真は新潮文庫「日本人は思想したか」梅原、中沢、吉本3氏の鼎談。和歌の起源、日本神話の特異性、日本仏教の特異性等、推薦の参考書。
●日本人の‘考える力’1~現実・潜在思念に即して考える実践思考力
歴史を振り返るならば、原始人は、原観念というべき「精霊」を生み出し、それを基礎に、様々な自然外圧を受けながらも生き延びるための実践思考を育んできた。
そうした実践思考が弓矢の発明以降、集団の膨張と、定住化という流れを生み出すと、集団間の緊張圧力を緩和するための、贈与等による超集団関係の構築へと舵をとった。ここでは、複雑な婚姻制へと発展しているケースもあるし、様々な神話により自我を戒めるための規範が語られるようになる。新石器時代、日本における縄文時代には、支配国家とは異なる道を歩んだという意味で、実践思考を超えた「社会を対象化した思考」の萌芽を感じ取ることが出来る。
そのような縄文的思考は、弥生以降、大陸から支配階級がやってきて、日本に私権統合と古代宗教を持ち込んでも、生き続けてきた。例えば、中国流の官僚制度=科挙は採用せず、統合の中心に保存された天皇制は社会統合に縄文以来の「女原理」を保存させてきた。
中央集権=官僚国家を拒んだ日本
天皇制が担っていた役割とは何か
また奴隷社会インドに生まれた仏教は、正邪の二元論を出発点とするために、仏になるために極めて高度な思弁や修行を必要とする。それに対して日本仏教は、即身成仏、悪人正機、全ての人は誰でも仏になれる、もっというと草木にも仏性があるという、縄文以来のアニミズムにどんどん接近していく。
日本人の観念探索は潜在思念と現実の肯定視を導いてきた
このように、渡来の私権制度・古代宗教を取り入れながらも、一貫して、具体的に自分たちの実感、潜在思念に合致するように、制度や思考を組み替えてきたのが、日本人であった。日本人が思考することを‘物を考える’というのは、縄文以来の伝統である、実践思考、潜在思念思考を踏まえての表現なのだろう。(西洋の技術は取り入れても思想はとりれないという和魂洋才という発想も、この流れにある)
ヨーロッパには俗に「神学論争」といわれる「教会の中でしか意味のない解釈論争」が存在するが、日本には現実・潜在思念と遊離して観念遊戯にふける、という伝統がない、ともいえる。この縄文以来の「現実・潜在思念」から遊離しない「実践思考」の伝統は、空虚な欺瞞観念から脱却し、充足発の肯定視空間を生み出し「共認の輪」を広げていく上で重要な資質といえるのではないか。
●日本人の‘考える力’2~不毛な争いを回避した超集団発想力
「支配して初めて考える」というのが古代宗教、近代思想の原点にあることは間違いない。しかし、縄文以来、「支配のための思考」はないものの「支配-被支配という関係を超えた、超集団の思考」は存在したのではないだろうか。
例えば、縄文時代の石器のデザインも土器のデザインも、その背景には、集団の移動や人口増加による、集団間の縄張り緊張圧力が関係している、といっていい。
>(縄文の)美の特質が最大限に発揮された地域は、縄文時代の中でも前期から中期にかけての東日本を中心とする地域だった。このころの東日本は・・・多くの人口が集中した地域だった・・・濃厚な縄文の美が生み出された基本的な条件は、人口の密集であったと考えられる。(進化考古学の大冒険 新潮社2009 松木武彦)
>異集団との遭遇がもたらした緊張が、実用性を離れた石器の精密・過大化、すなわち「過剰デザイン」を生んだのではないか。(日本人とは何か 柏書房2010 安斎正人)
縄文デザインは、集団を超えた共通コードを持ちつつ、各集団において独自性を発揮し、いわば、縄文精神の表現度を競い合っているかのようである。これは一種のより広く、深い共認充足を求め合う共認闘争関係である。
写真はhttp://www.asahi-net.or.jp/~eg7k-kbys/doki.html様よりお借りしました。
こちらのHPにも書かれていますが、縄文デザインは日本が世界に誇る芸術品です。
そして、その後の古墳が世界においても郡を抜いて巨大化していったのも、各豪族が、不毛な争いを回避し、談合し、その談合力を土木工作物の大きさとして競い合った結果、だとみることもできる。
さらには南北朝の対立、明治維新という大混乱においてさえ、結果的に敵対勢力を排除することなく、むしろ敗者の怨霊を畏れ、祀りながら、国家統合を図ってきた。本来、日本神道の本質は、敗者のルサンチマン=自我が暴走することを抑えこむところにある。(被征服者、私権闘争の敗者に対する惧れを表明した外来信仰のみが日本の信仰として定着することも可能となったともいえる。)
いいかえれば剥き出しの「力の原理」主義者は、ほとんど存在せず、常に、和平的統合を追求してきたともいえる。その日本がアメリカ発の「新自由主義者」=力の原理主義者たちに蹂躙されているという現在的矛盾はあるものの、むしろ、日本はアメリカ発の力の原理主義者が敗北すれば、世界共認をリードしていける可能性があるのではないだろうか。
◎シリーズの予定
以下、本シリーズの予定を示しておきます。(ただし、あくまでも予定です。)
1.序:追求の目的と視点 8・13
2.縄文土器、土偶にみる縄文人の思考力 8・18
3.銅鐸、銅剣、銅鏡にみる弥生人の思考力 8・25
4.日本神話にみる国家統合の思考力1(スサノオ、オオクニヌシ神話) 9・1
5.日本神話にみる国家統合の思考力2(天孫降臨神話) 9・8
6.万葉集とかな文字の誕生にみる万葉人の思考力 9・15
7.中世惣村の誕生と観念力の大衆化 9・22
8.鎌倉仏教~仏教の日本的受容の変遷 9・30
9.南北朝は何を争い、いかに収束したか 10・6
10.能や狂言にみる日本的芸能の思考力 10・13
11.国学に見る日本人の観念力 10・20
12.江戸=脱戦争の思想 10・27
13.幕末の政治思想とは何だったのか? 11・3
14.日本人の観念力の正体とその可能性 11・10
■
学者による集落論第3回【縄文の集団に学ぶ~その8】水野家族論って本当?
>次回は、水野家族論の紹介を通じて、縄文集落の有り様をさらに解明していきましょう!<
学者による集落論第2回【縄文の集団に学ぶ~その7】和島家族論って本当?
というさーねさんからのバトンを受け、
るいネットより水野家族論を見ていきましょう。
前回の和島家族論を要約すれば、集団婚を経て対偶婚、家父長制大家族、そして小家族へ、というのが原初的な家族の大まかな発展の図式であり、そこには『家族・私有財産・国家の起源』におけるF・エンゲルスの、「血縁家族―プナルア家族―対偶婚家族―家父長制家族―一夫一婦制家族」という進化主義的家族観の強い影響がうかがえます。
一方、水野正好の家族・婚姻観の輪郭は、かれの最初の試論、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』の中にすでに明確な形、つまり、「二棟一家族論」と「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」として現れており、水野集落論全体を貫く基本的なモティーフとして今日へと続いています。
といったように水野氏は和島氏とは全く違ったアプローチでの「家族論」を展開しています。では、水野氏の提示する家族論の背景となるものはなんだったのか?について見ていきたいと思います。以下、要約版です。
1・縄文時代では集団婚が支配的であるとした和島に対し、同居制にもとづく、おそらくは単婚的な「小家族」がすでに登場をみていた可能性が指摘されています。しかも、「性別ないし機能集団」としての性格も考慮されています。この「小家族」は二軒の住居を一単位として成立するものであったことを、与助尾根集落におけるいわゆる「小群」の分析結果にもとづいて明らかにしたのです。
2・二軒を単位とする「小家族」のさらに上位には、埋葬・消費・政治の基本単位としての「家族」が存在していた可能性を、六軒の住居、つまり三小群から構成される「大群」との関連において指摘しました。
3・こうした三小家族―六軒の住居を包摂する「家族」すなわち「大群」は、東群と西群の併存現象にもうかがわれるように与助尾根では合計二群存在し、両群が一体となって「部族」としての「集落」全体を構成するという、立体的な縄文集落像を呈示したのです。
4・集落―大群―小群という重層的な群構成と部族―家族―(単婚?)小家族(または性別ないし機能集団)というレベルの異なる社会集団とを重ね合わせた水野は、続けて与助尾根における祭式を集落そのものに基盤を置く「広場祭式」、集落~大群間に基盤を置く「葬送祭式」、大群~小群間に基盤を置く「石柱・石棒・土偶祭式」の三類に分類し、全体として与助尾根の集落構造と宗教構造とを一体的に復元しようとしたのです。
5・住居出土の特殊な付属施設をもとに措定した大群~小群間に基盤を置く各祭式の性格を、狩猟神・祖家神にもとづく男性祭式としての石柱祭式、性神・成育神にもとづく同じく男性祭式としての石棒祭式、穀神・母神にもとづく女性祭式としての土偶祭式としてそれぞれ位置づけ、内容・形態を異にする以上の各祭式が各小群に分掌されるという、祭祀論に大きく立脚した特異な家族像を想定しています。これが「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」なのです。
与助尾根の集落分布から導き出された「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」ですが、この説は大きな問題を孕んでいるようです。水野家族論は1930年に宮坂英弌氏によって発掘された情報を基に1969年に纏められたものであるが、1998年に行われた試掘調査によって新たな遺構の分布が明らかになっている。
①1998年の調査で新たに発見された遺構を加えると39軒まで増加する。
②1930年の調査住居は実際の位置とズレがある。
③各住居の所属時期は、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在として見なしている。
④新たに発見された11軒のうち4軒は住居群の北側に分布し水野の言う集落全体(二大群12軒)―大群(三小群6軒)―小群(2軒一単位)という集落分割案では説明できない位置にある。
⑤東西に細長い台地に沿って弧状に広がると考えられていた与助尾根集落は、略環状、ないし北東に開く馬蹄形状を呈していた可能性が強く、新たな視点からの検討が必要。
これに対し、佐々木藤雄氏は次のような厳しい言葉を述べている。
>一体、どのような詭弁を弄すれば、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在例とみなすことができるのであろうか。想念の集落論と呼ばれる水野集落論の恣意性と主観性が、ここにはもっとも集約的な形で表出されていたといっても過言ではない。
与助尾根遺跡を舞台にした今回の試掘作業の結果は、歴史的な真理の究明よりも誤謬だらけの学史や定説の賛美と絶対化を繰り返す与助尾根集落論、否、日本考古学そのものへのまぎれもない鎮魂歌、レクイエムであったといわなければならない。<
与助尾根集落論―もう一つの「不都合な真実」より引用。
これまで「和島家族論」「水野家族論」を中心に学説を見る中で、様々な切り口からの仮説の提示こそあれど、どこか権威主義的・時には他者の意見を否定してでも自分の説を際立たせようといった手法まで垣間見られる。学者はその分野単独の知識としては長けている一方で、それ自体を職業にするが故にそういった偏った思考に陥りやすいといった構造にあることも否めないと感じた。
今後の追求ではそれ自体を生業としない、素人だからこそ見える視点・本当の事実はなんなのか?また、そこから見えてくる日本人のもつ特性・これからの可能性